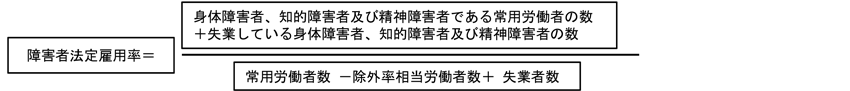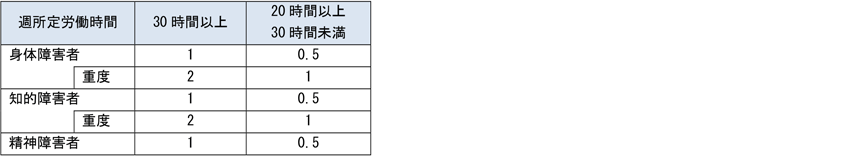-
2018.05.16
セクハラの防止措置などを再認識しましょう
セクハラを問題に辞任のニュースが記憶に新しい現在、被害者への配慮(プライバシーの保護など)が必要とされることなどを再認識された方も多いのではないでしょうか。厚生労働省の「事業主向けのセクシュアルハラスメント対策」のパンフレットでも、対策の一つとして「当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知」が必要としており、これを機に、今一度、どのような行為がセクハラに該当するのか、どのようなセクハラ防止措置を講ずる必要があるのかなど、セクハラに関する基本事項を確認しておきましょう。
職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な対策をとることは事業主の義務です。必要な措置は10項目あります。
■事業主が雇用管理上講ずべき措置とは
職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、厚生労働大臣の指針により10項目が定められており、事業主は、これらを必ず実施しなければなりません。企業の規模や職場の状況に応じて適切な実施方法を選択できるよう、具体例を示しますので、これを参考に10項目を実施してください。なお、派遣労働者に対しては、派遣元のみならず、派遣先事業主も措置を講じなければならないことにご注意ください。
また、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止の効果を高めるためには、発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要です。セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景には、性別役割分担意識に基づく言動もあると考えられ、こうした言動をなくしていくことがセクシュアルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることに留意しましょう。
会社は、日頃から労働者の意識啓発など、周知徹底を図るとともに、相談しやすい相談窓口となっているかを点検するなど普段から職場環境に対するチェックを行い、特に、未然の防止対策を十分講じるようにしましょう。
まず、10項目のポイントは以下の通りです。1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2)セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)相談窓口をあらかじめ定めること。
(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。3 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(6)事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
(7)事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(8)再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)4 1から3までの措置と併せて講ずべき措置
(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
(10)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
-
2018.03.29
健康寿命は男性72.14歳、女性74.79歳
厚労省は9日の「健康日本21(第二次)推進専門委員会」で、平成28年の健康寿命の推計値を公表した。男性は72.14歳、女性74.79歳となり、前回25年の71.19歳、74.21歳よりも+0.95歳、+0.58歳と男女とも延伸している。最長は男性は山梨の73.21歳、女性は愛知の76.32歳、最短は男性は秋田の71.21歳、女性は広島の73.62歳。28年の平均寿命は男性80.98歳、女性87.14歳で、健康寿命との差は男性8.84歳、女性12.35歳となった。
-
2018.03.29
介護施設等従事者の高齢者虐待が10年連続増加
厚労省は9日、平成28年度の高齢者虐待の調査結果を発表した。介護サービス事業所・施設などの従事者と、家族など養護者による虐待の判断件数の合計は1万6836件となり、過去最高になった。特に施設等従事者の虐待は10年連続で増加し、前年度から44件増えて452件となり、過去最高になった。
-
2018.02.26
障害者雇用率が2.0% ⇒ 2.2%へ引き上げ (平成30年4月1日施行)
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.0%)以上の障害者を雇うことを義務付けており、厚生労働省が取りまとめた、平成29年の「障害者雇用状況」集計結果では、法定雇用率達成企業の割合は 50.0%(対前年比1.2ポイント上昇)となっています。
そして、平成30年4月1日より、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることになったことに伴い、障害者法定雇用率が2.0%から2.2%(民間企業)に引き上げられます。
1. 障害者雇用率について
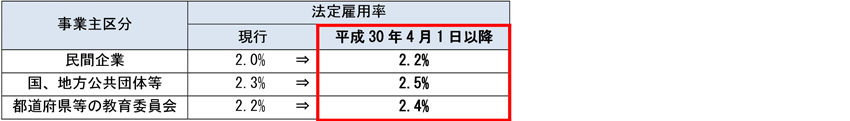
【表】障害者雇用率
(1) 一般民間企業における雇用率設定基準

【図】障害者法定雇用率
(2) 障害者雇用率のカウント
法定雇用率は原則として、週30時間以上働く障害者は1人、週20時間以上30時間未満働く障害者は0.5人に換算して算出されますが、4月以降は精神障害者に限り、週20時間以上30時間未満の労働でも雇用開始から3年以内か、精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内の人は1人と数えることとする特例措置を設けました。これは5年間の時限措置となります。

【表】週所定労働時間
2. 対象となる事業主の範囲について
法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。対象となる事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。3. 今後の引き上げについて
平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。 具体的な引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされることとなっており、2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html) -
2018.02.14
障害サービス報酬改定の概要を公表
厚労省は5日、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要を公表した。全体の改定率は0.47%の引上げで、新サービスが4月からスタートする。障害者の重度化・高齢化や医療的ケア児への支援などの課題に対応する。28年5月に成立した改正障害者総合支援法で新しくつくられた「自立生活援助」「居宅訪問型児童発達支援」「就労定着支援」の3サービスの基準・報酬を設定する。地域共生社会の実現に向け、介護保険と同様に「共生型サービス」の基準・報酬も設定する。